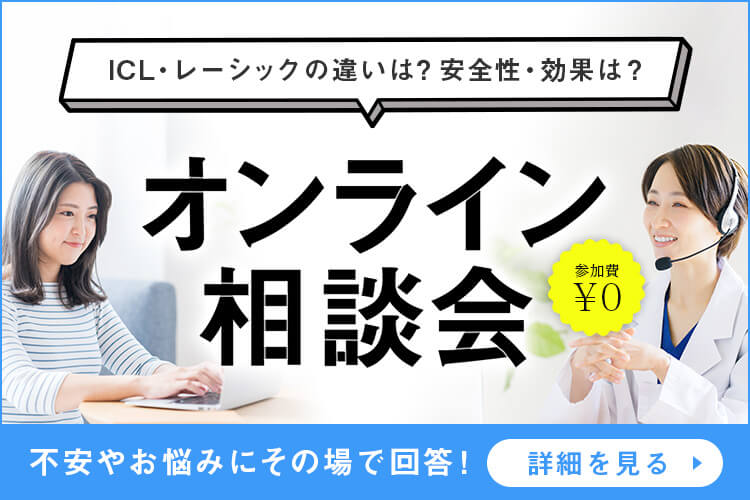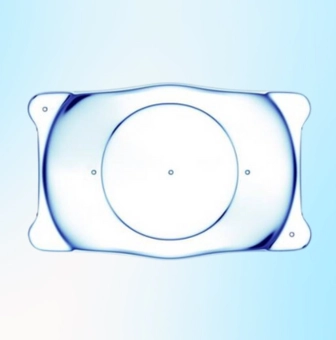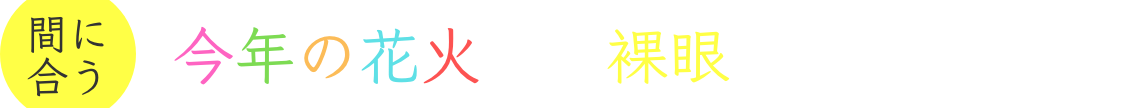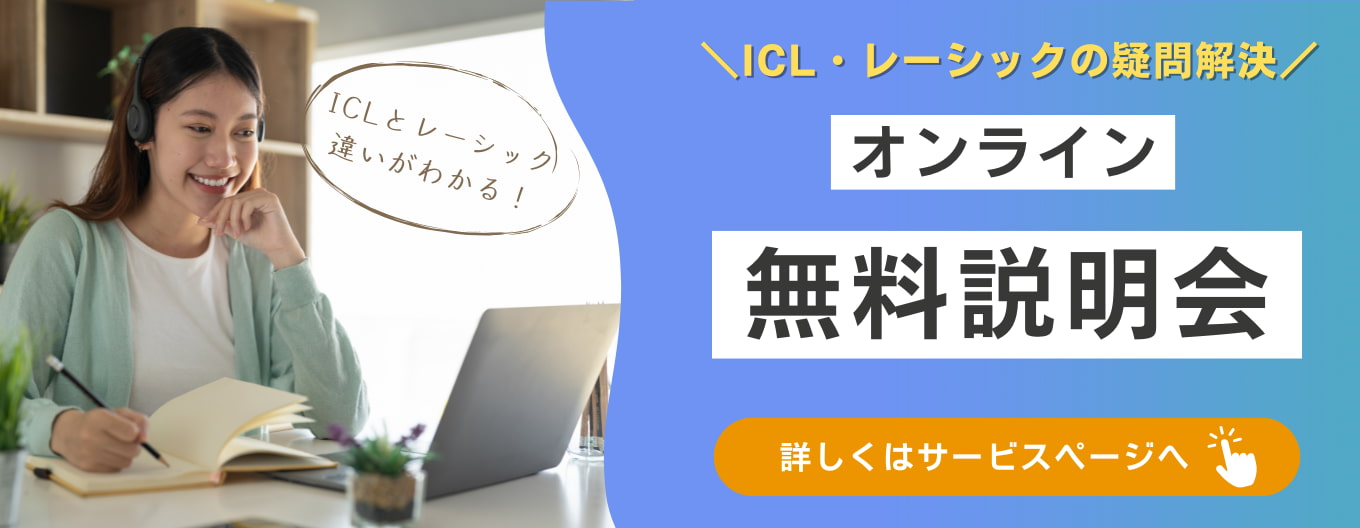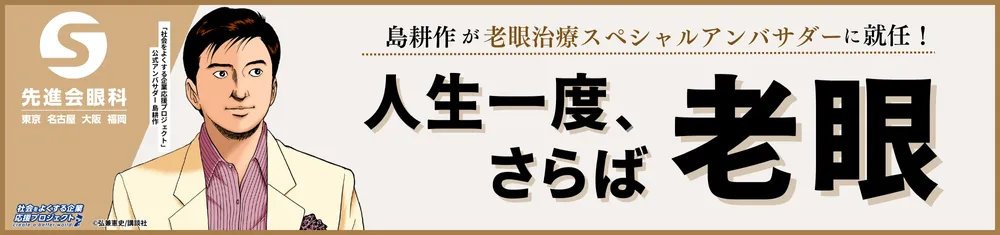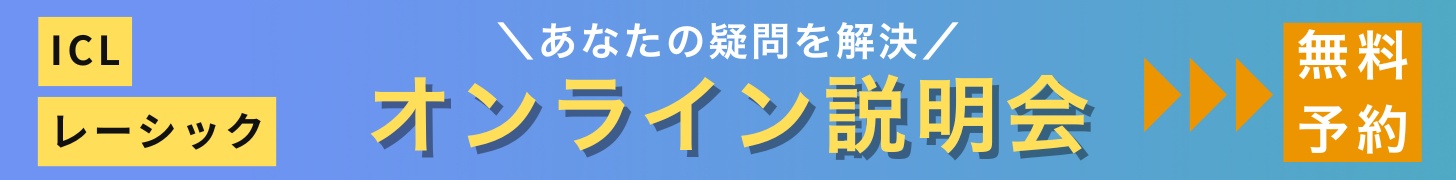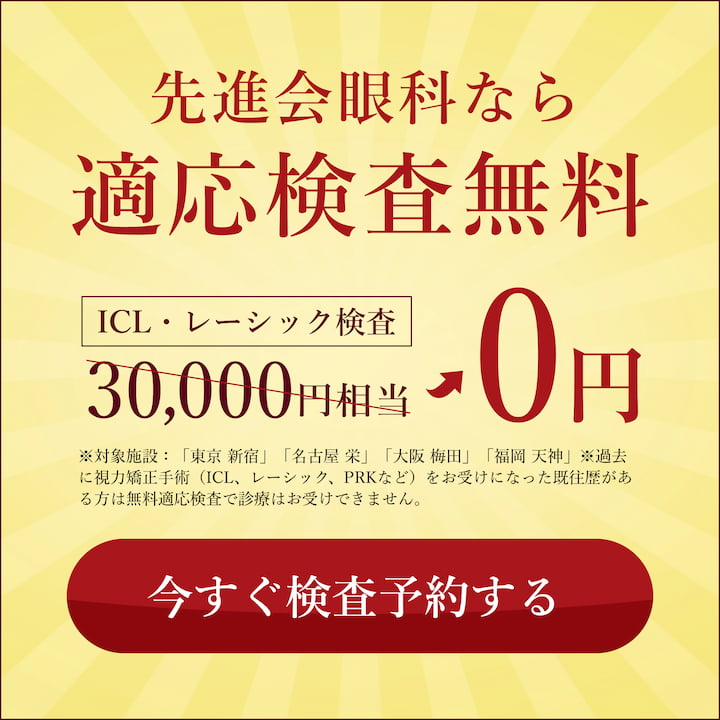老眼にならない人の特徴は?近視と老眼の関係性も解説

老眼は加齢による自然な現象で、誰にでも起こります。しかし、「近視の人は老眼にならない」と言われることもあるため、「老眼にならない人もいるのではないか」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これは誤解で、実際には近視の方は老眼にならないのではなく、近くのものにピントが合うため、老眼の症状に気づきにくい(老眼症状が出にくい)傾向にあるだけです。
この記事では、老眼を自覚しにくい方の特徴から、近視と老眼の関係ついて詳しく解説します。
老眼とは

老眼とは、加齢により水晶体がかたくなり、目のピント調整機能が衰えることによって、近くのものが見えにくくなる老化現象の一つです。
ピントの調整機能が低下すると、遠くから近くへと目線を移したときにピントが合うまでに時間がかかり、視界がぼやけてしまいます。具体的には、以下のような症状が現れます。
・距離を離さないと小さい字が読みづらい
・暗い場所だとものが見えにくい
・手元がよく見えない
また、一般的に「老眼は40代から始まる」といわれていますが、近年では、若年層にも老眼の症状を自覚する方が増えてきました。その理由として、スマートフォンの長時間使用が挙げられます。
スマートフォンを至近距離で見つづけることで、目のピント調整機能が一時的に低下し、老眼に似た症状が現れてしまうのです。これは一時的な症状なので、目を休ませれば機能はすぐに回復しますが、同じ症状が何度も現れてしまうと、若くても老眼の症状が進行する可能性があるので注意してください。
また、近視や遠視、乱視といった目の屈折異常や、メガネやコンタクトレンズでの矯正の程度・方法によって、老眼の感じ方は異なります。なかには老眼になりにくい人もおり、老眼の症状は、年齢や習慣により感じ方や現れ方の個人差が大きいといえます。
【関連記事】
老眼とは?何歳から始まる?原因や症状、進行を遅らせる方法を解説
水晶体の構造と役割|水晶体の病気の原因と治療法も解説
老眼の始まる時期
先述した通り、「老眼は〇歳から」と一括りにはできないものの、一般的に老眼の自覚症状を感じるのは40歳前後からです。
まず、近距離のピントが合いづらくなり、スマートフォンなどに表示される小さな文字が読みづらくなってきます。そして、年齢を重ねるにつれ、徐々にピントが合う距離が遠くなっていき、近くのものがより一層見えづらくなるわけです。
以下の表に、年代別に目のピントを合わせられる距離をまとめたので、参考にしてみてください。
▼年代別のピントが合う距離
| 年代 | ピントが合う距離 |
|---|---|
| 40代前半 | 30cm以内 |
| 50代前半 | 40cm以内 |
| 50代後半 | 60cm程度 |
| 60代以上 | 腕を伸ばした距離 |
上記の表を見るとわかるように、老眼は40代からゆっくりと確実に進行していき、60代後半で老眼の進行はストップします。
老眼を自覚しにくい(老眼症状がでにくい)人の特徴

老眼の進行は個人差が大きく、一般的な発症時期である40代でも老眼の兆候がみられない人もいます。以下に、そういった老眼症状がでにくい人の特徴をまとめたのでご覧ください。
老眼になりにくい人の特徴
- 目に対する紫外線対策を実施している
- 視力に適した矯正を行っている(メガネ、コンタクトレンズなど)
- 健康的な生活を心がけている
- スマートフォンの長時間使用を避けている
上記の特徴は、どれも目を酷使しない点が共通しています。老眼の進行を遅くするためにも、目にかかる負担を最小限に抑えることをおすすめします。
近視の人は老眼にならない?
「老眼は近くのものが見えにくくなる症状だから、遠くのものが見えにくい近視だったら老眼にならないのでは?」と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、先述した通り、近視の人は老眼にならないのではなく、老眼の症状に気づきにくいだけなのです。
なぜ気づきにくいのかというと、ピント機能の低下は、正視、近視、遠視問わず進行には差がないからです。近視の人もピント調整機能は衰えており、実際には老眼の症状は現れています。ところが、近視の人は、もともと近距離にピントが合っているため、ピント調整機能が低下しても、近いものはよく見えることから、老眼の症状に気づきにくいというわけです。
近視だからといって油断せず、40代からは老眼になることを意識して、目に負担をかけない生活を送ることを心がけていきましょう。
老眼のセルフチェック方法

「近くが見えづらい」、「視界がかすむ・ぼやける」などといった、視力の違和感を覚えたら、老眼が始まっているサインかもしれません。
以下に、老眼のセルフチェック項目をまとめたので、ぜひチェックしてみてください。
老眼の症状チェックリスト
- 小さな文字が見えにくい
- 本を読むとき、遠ざけるとよく見える
- 夕方になると目が疲れる
- パソコンやスマートフォンを使用するとすぐに目が疲れる
- 部屋の中が今までよりも暗く感じる
- 文字を読んだあとに頻繁に肩がこる
- 細かい手作業が難しくなった
上記のチェック項目に2つ以上あてはまる場合は老眼の可能性があるので、眼科医に相談することをおすすめします。
老眼になる原因

老眼になる原因は、加齢に伴う目の水晶体の硬化や、毛様体筋(もうようたいきん)の衰えです。
水晶体はレンズの役割を果たしており、毛様体筋はその水晶体を調整して、ピントを合わせる役割を担っています。近くを見る際には、毛様体筋が収縮し、水晶体を厚く調整してピントを合わせようとする仕組みです。
この水晶体が硬くなったり、毛様体筋の動きが低下したりすると、適切にピントを調整できなくなり、近くのものが見えにくくなります。これが、老眼というわけです。
老眼を予防する方法

老眼は、症状が現れていないうちから早めに予防しておくことをおすすめします。また、老眼が始まった方でも、以下にご紹介する予防法に取り組めば、老眼の進行を遅らせる可能性が高まりますので、ぜひお試しください。
食事の内容を見直す
まずは、食事の内容を見直して、各種栄養をバランスよく摂取できるよう心がけていきましょう。栄養の偏りがなくなり、血行が良くなると、目にも栄養が行き渡って疲れ目やドライアイなどが起こりにくくなります。
また、目の疲れに効果があるといわれている、抗酸化物質を含んだ食品を積極的に摂取することもおすすめです。以下に、目を健康に保つ効果が期待できる栄養素をまとめたので、お役立てください。
▼目に効果がある栄養素
| 成分 | 働き | 含む食材 |
|---|---|---|
| ルテイン | 強い抗酸化作用により、水晶体を守る | ほうれん草、ブロッコリー、芽キャベツ |
| アントシアニン | 抗酸化作用をもち、目の疲れを軽減する | ブルーベリー、ぶどう、黒豆 |
| コエンザイム | 強い抗酸化作用をもつ | いわし、さば、うなぎ、牛肉、豚肉 |
| ビタミンA | 皮膚や粘膜の健康を保持し、ものを見る際の明るさを保つ | にんじん、小松菜、レバー |
上記の栄養素を含んだ食品を取り入れ、栄養バランスのとれた食事を継続していけば、目の健康を、長く維持できる可能性が高まるでしょう。
目のストレッチを行う
ストレッチには、目の筋肉をほぐし、硬化を防ぐ効果があります。目のストレッチを行って、目の筋肉にかかる負担を軽減させましょう。ここでは、ペンと老眼鏡を使ったストレッチ方法をご紹介します。
ペンを使う方法
ペンを使ったストレッチ方法は、以下の通りです。メガネやコンタクトレンズを使用している方は、つけたままストレッチを行っていただいて問題ありません。
目のストレッチ方法
- ペンを持って腕を前に伸ばす
- ペンの先端を数秒見る
- ペンの先端より奥の景色を数秒見る
就寝前に上記のストレッチを、3セット行えると理想的です。仕事の休憩時など、時間に余裕ができた際に取り組むのもよいでしょう。
老眼鏡を使う方法
次に、老眼鏡を使ったストレッチの方法をお伝えします。100円均一ショップで売っている老眼鏡で構いませんので、用意してお試しください。
老眼鏡で毛様体筋をほぐすストレッチ
- プラス2度の老眼鏡を用意する
- 老眼鏡をかける(メガネやコンタクトレンズをつけている場合は、その上から)
- 老眼鏡を通して、1m以上離れている景色をゆっくり眺める
このストレッチによって、毛様体筋の緊張と緩和が繰り返されるため、効率よく毛様体筋がほぐれます。頻度としては、1日1セット10回くらいを目安に取り組むことをおすすめします。
まとめ

この記事では、老眼を自覚しにくい(老眼症状がでにくい)人の特徴や、近視と老眼の関係、さらには老眼予防の方法について詳しく解説しました。
老眼になりにくい人は、紫外線対策や健康的な生活などを意識して、目の健康を保つことを習慣づけています。また、近視の人は老眼にならないわけではなく、老眼の症状は進行していても、気づきにくいだけというのが事実です。この記事を読んで、目の老化現象を可能な限り抑えられるように、今からできることを行っていきましょう。
先進会眼科は、20年以上に渡る治療実績に裏打ちされた、皆様から信頼される眼科医療をご提供します。老眼の治療にも対応していますので、ぜひ気軽にご相談ください。
視力回復・白内障など目の治療なら
先進会眼科へご相談ください
ご予約はお電話、Web予約、LINEで承っております。診療に関するご質問ご相談はLINEでのみ受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

日本眼科学会認定眼科専門医
日本白内障屈折矯正手術学会 理事
先進会眼科 理事長
略歴
聖マリア病院 眼科 外来医長
福岡大学筑紫病院 眼科
村上華林堂病院 眼科
福岡大学病院 救急救命センター
福岡大学病院 眼科
愛知医科大学卒業
福岡県立嘉穂高校卒業
医師資格番号
医師免許番号 381664
保険医登録番号 福医29357
先進会について

先進会眼科はレーシックやICL(眼内コンタクトレンズ)、レーザー白内障治療、ドライアイ治療、円錐角膜治療など、様々な治療や手術を全国でおこなっています。
「自分が受けたい眼科治療」をテーマに最善の方法をクリニック一丸となり、また多くの医師やスタッフも視力回復手術を受けて、患者様に寄り添った治療、最高のおもてなしを提供できるよう、日々努めています。
当院のコンテンツ作成について

当ページは、医療広告ガイドラインを遵守し、当院の医師による監修のもと掲載しています。
皆さまに正しく役立つ情報をお届けするため、記事の企画は当院スタッフで行い、執筆は外部の提携ライターに依頼しています。完成した記事は当院ドクターが医学的な正確性を確認し、さらに薬事法に抵触していないか専門機関による厳正なる確認を経て公開しています。